
名付けられたものとの境界に目をこらし、いわく言いがたいものに形を与えようとする作家らの営みが静かな余韻を残す。埼玉県立近代美術館(さいたま市)で開かれている「イン・ビトウィーン」(2024年1月28日まで)は、この5年ほどの間に収集した3作家と現代アーティスト1人によって構成した展覧会。既存のコレクションを活用しながら現代を照射する視点を探ってきた同館ならではの企画だろう。
展示は1970~80年代にかけて作品を手がけた林芳史(43~2001年)から始まる。在日韓国人2世として大阪に生まれた林は早稲田大で学び、20代で日本国籍を取得した。東洋思想をベースとした美術批評や、墨と和紙を用いた作品に、アイデンティティーの所在を問い続けた姿が重なる。日用品に紙をあて、鉛筆でこすって形をうかびあがらせたフロッタージュ作品が印象的だった。例えばハサミを写し取った「Work」(1975年)は、やわらかな筆跡がハサミの物質性と紙に表れたイメージの境界をあいまいにしていた。大宮市(現さいたま市)に生まれ、「もの派」を代表した関根伸夫と深い親交を結んだ縁で収蔵に至ったという。
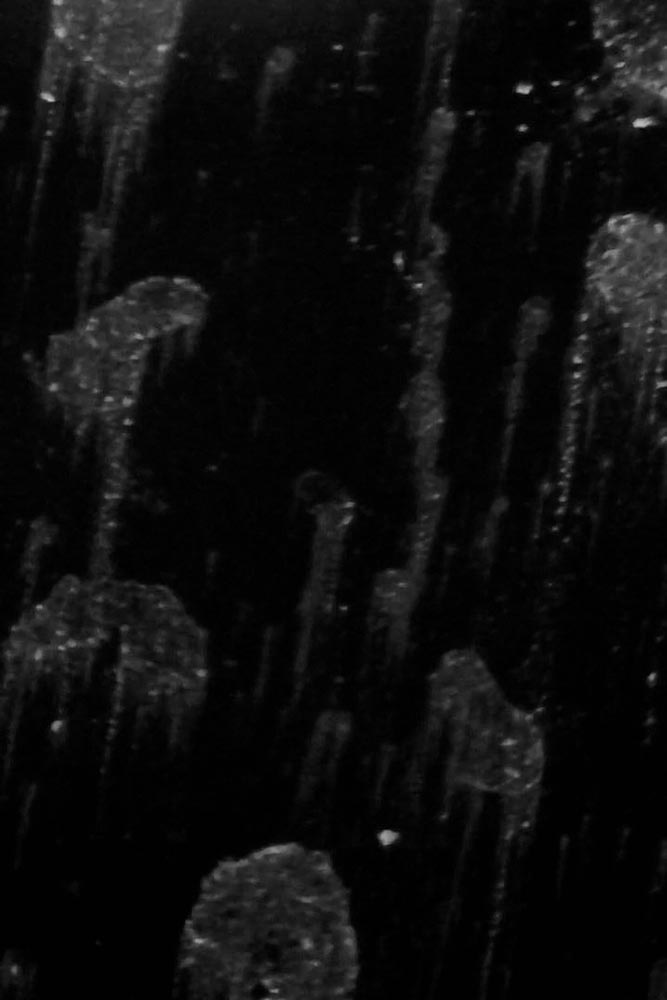
ゲストアーティストとして参加した潘逸舟(はんいしゅ)(87年生まれ)が続く。中国・上海に生まれ、9歳のころ家族と日本に移り住んだ。「家を見つめる窓」(2023年)は、コロナ禍の上海、隔離されたホテルで撮影した映像の新作だ。マクロカメラは、窓の向こうは映さず、ひたすらガラスにこびりついた無数のちりや汚れを捉える。潘は「窓は生家の方を向いていたような気がする」といい、懐かしさと同時に故郷への複雑な距離感が浮かぶ。

4人のなかで特に異彩を放っていたのが埼玉県飯能市で暮らした画家、早瀬龍江(1905~91年)だ。前衛画家、福沢一郎に学び、シュールレアリスム絵画を描いた。刻々と変化する、自身と思われる女性像は、50代のものになると抽象度をぐっと高め、腕や乳房といった身体のパーツが引きちぎられたようにばらばらに分解されていく。身体をめぐる不可視の世界をすくいとろうとした試みが生々しい。

最後のジョナス・メカス(22~2019年)はナチス・ドイツの迫害を逃れて祖国リトアニアからアメリカへと渡った詩人で映像作家。自分自身の居場所を確かめるように、街行く人々や家族に16㍉フィルムカメラを向けた。
メカスの映像作品に使われているささやかな音楽が会場全体にもれて響き、本展に優しげな一体感を与えていた。同館の鴫原悠(しぎはらはるか)学芸員は「いずれの作家も日常と非日常、過去と現在、国境やジェンダーなど、目に見えない境界線のあわいに立って制作した」と語る。時代や背景が当時とは異なっても、その誠実なまなざしは切実に映る。
◇開催中「さいたま国際芸術祭」
さいたま市では、12月10日まで「さいたま国際芸術祭2023」が開かれている。前身の「さいたまトリエンナーレ」を含めて3回目となり、ディレクターは同市にアトリエをかまえる気鋭のアートチーム「目[mé]」(以下「目」)が担った。

メイン会場「旧市民会館おおみや」には、見慣れた風景を異化してあっと驚かせてきた「目」らしい仕掛けが施された。透明の板で空間を自在に仕切り、「会場導線」を設けたのだ。その板越しに見るものは作品であろうとなかろうと特別なものに思えてくるから不思議。見る人も、見られる存在となり、芸術祭を構成する一部となる。ありふれた日常に出会い直し、新鮮な風が吹き込んでくるような体験ができる。
2023年11月27日 毎日新聞・東京夕刊 掲載
